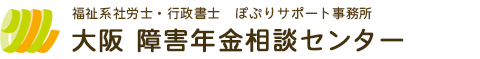よくある Q&A
(1) 障害年金がもらえるかどうかを知りたいのですが?
(1) 3つの要件に該当している場合にもらうことができます。
(2) 既に65歳を過ぎているのですが、障害年金は今からでは請求できますか?
(2) 年齢だけで決められるわけではありません。一定の条件に該当していれば65歳を過ぎてからでも請求できる場合があります。
(3) 障害年金をもらうためには、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉の手帳が必要ですか?また手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?
(3) 障害年金と手帳の制度は別の制度です。
手帳の取得は必ずしも必要ではなく、また等級も年金と手帳では違う場合が多く存在します。
(4) 障害年金がもらえない病気(病名)がありますか?
(4) 障害年金は病名によって出るのではなく、労働の制限や日常生活の支障を基準に支給されるものです。原則的にはすべての傷病が障害年金の対象となります。
(5) 障害年金を請求したら、いつからもらうことができるのですか?
過去の分を遡って請求できると聞きましたが、どんな場合にできるのでしょうか?
(5) 事後重症の場合は、請求した月の翌月分からの支給となります。
障害認定日に障害の状態であったことが認定された場合には、最大5年分の遡った受給ができます。
(6) 障害年金請求のための書類はどこでもらったらいいのでしょうか?
(6) 年金事務所(旧 社会保険事務所)か、市区町村役場の年金担当課です。
日本年金機構のホームページからダウンロードできるものもあります。
障害年金がもらえるかどうかを知りたいのですが?
一律にお答えすることができません。
以下の4つのことをまず教えてください。
- 1その障害のもとになった病気やけがで初めて病院にかかった日(初診日)はいつですか?それ以降の通院、治療暦は?
- 2初診日は何歳の時ですか?
加入していた年金制度は国民年金ですか?
厚生年金ですか?
- 3その2ヶ月前までに年金保険料をどれくらい納めていましたか?
- 4現在の障害の状態は?
働くことや日常の生活にどのような支障がありますか?
検査の数値結果がわかりますか?
- 5現在の年齢は?

まず、その障害の元になった病気やけがで初めて病院にかかった日(初診日)がいつなのかを調べてください。
関連した傷病がある場合はその病気で初めて受診した日が初診日になり、社会的治癒があった場合は再発後の受診日が初診日になります。
次にその初診日が20歳以降の場合は、その2ヶ月前までに、年金の保険料をどのくらい納めているか(保険料要件)を調べる必要があります。
納付要件を満たしていないと障害年金は支給されません。
初診日が65歳以降で被保険者ではなかった場合、また60~65歳であっても老齢年金の繰上げ請求をしていた場合は、障害年金を受給することができません。
そして、障害認定日の障害の状態が初診日に国民年金に加入されていた(または20歳未満か60歳~65歳で被保険者ではなかった)場合は、1・2級、厚生年金に加入されていた場合は1~3級の障害認定基準の状態に該当している場合に年金は支給されます(本来請求、認定日請求といいます)。
障害認定日以降に状態が悪くなって等級に該当した場合(事後重症といいます)は、65歳になる前に障害年金の請求をしなくてはなりません。
これは、高齢になって働けなくなった場合の保障は老齢年金でカバーしている。
障害年金は基本的には老齢年金がもらえる年齢になる前に病気やけがで働けなくなったり、生活に支障がある障害をもった方への保障として考えられているためです。
これを読んでもよくわからない場合は、ひとまずご相談ください。
また、お答えできるのは「受給の可能性があるかどうか(見込み)」についてであり、受給についての最終的な判断は厚生労働省がするものであるということをご了承ください。
既に65歳を過ぎているのですが、障害年金は今からでは請求できないのですか?
年齢だけで決められるわけではありません。
一律に年齢制限があるわけではなく、一定の条件に該当していれば65歳を過ぎてからでも請求できる場合があります。
障害年金は基本的には、老齢年金がもらえる年齢になる前に病気やけがで障害の状態になった方を対象としています。
初診日に国民年金または厚生年金の被保険者であること、または60歳~65歳で日本に在住し、老齢年金の繰上げ請求をしていないこと(繰り上げ請求をすると65歳になったのと同じ扱いになります)、または20歳未満であった(年金制度に加入していなくて当然である)ことがまずは条件となります。
また、障害認定日(基本的には初診日から1年6ヶ月を経過した日、20歳前障害の場合は20歳到達時)に障害の状態でなかった方が、その後状態が悪くなった場合(事後重症)は、65歳の誕生日前に請求しなくてはなりません。
しかし、例えば初診日が年金制度加入中で障害認定日に障害の状態であった場合や昭和61年3月31日までに20歳になった方で20歳時点で障害認定基準の障害年金がもらえる等級に該当する状態であった方(そのことを証明できる診断書の取得が必要です)は、現在65歳を過ぎていても障害年金を請求することができます。
詳しくはご相談ください。
障害年金をもらうためには、身体障害者や精神障害者保健福祉の手帳が必要ですか?また、手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?
障害年金と手帳の制度は別の制度です。手帳の取得は必ずしも必要ではなく、また等級も年金と手帳では違う場合が多く存在します。
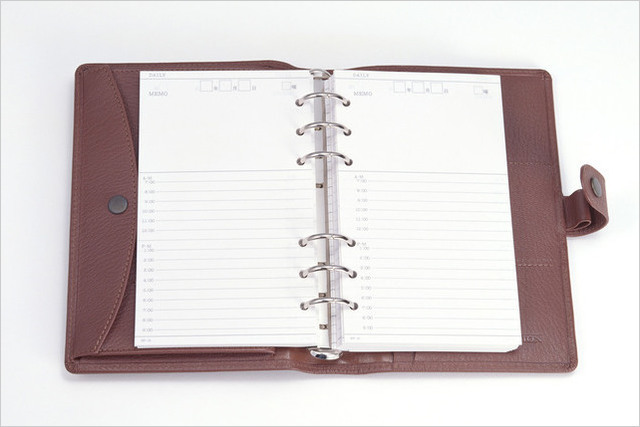
年金事務所や市区町村役場で手帳を取得しているかと聞かれたり、先に手帳を取得されたほうが申請がスムーズだと言われることもあるようですが、手帳を持っていないと年金が申請できないということはありません。診断書での判断となります。
また等級についても、手帳と年金は同じではありません。例えば心臓にペースメーカーを入れた場合、身体障害者手帳では1級となりますが、障害年金では基本的に3級として扱われます。反対に4級の身体障害者手帳をお持ちの方が2級の障害年金を受給できたというケースもあります。
また、難病の場合は身体障害手帳が交付されないことがありますが、障害年金を受給できないわけではありません。精神障害者保健福祉手帳の障害認定基準と、精神障害による障害年金の障害認定基準の等級は、ほぼ同じです。
障害年金がもらえない病気(病名)がありますか?
障害年金は病名によって出るのではなく、労働の制限や日常生活の支障を基準に支給されるものです。原則的にはすべての傷病が障害年金の対象となります。
病名、障害名によってもらえる、もらえないが決まるのではなく、その病気やけがによる障害の程度(検査の数値や日常生活への支障、労働能力など)がどの程度なのかによって決まります。そのことを医師に診断書にきちんと書いてもらうことがポイントです。
ただし、精神障害の場合は、障害認定基準において
- 「人格障害は原則として認定の対象とならない」
- 「神経症にあたっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則手には認定の対象とならない。ただしその臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は躁うつ病に準じて取り扱う」
とされており、病名によって障害年金が支給されにくいものがあるのが現状です。
また、薬を飲むことによってコントロールできる病気については、薬を飲んでもなおコントルできない場合に対象となります。
障害年金を請求したら、いつからもらうことができるのですか?
過去の分を遡って申請できると聞きましたが、どんな場合にできるのでしょうか?
事後重症の場合は、請求した月の翌月分からの支給となります。
障害認定日(リンク)に障害の状態であったことが認定される場合には、遡った受給ができます。

障害認定日に障害の状態でなかった場合や、その時の診断書が取れない等の場合(事後重症)は、請求した翌月分から受給できることになります。
障害認定日に障害の状態であったことが認定される(認定日請求)と障害認定日の翌月分からの受給ができます。ただし、時効があり最長でも5年分しか支給されません。
請求してから実際に年金が振り込まれるまで、国民年金ではおおむね3ヶ月、厚生年金では6ヶ月程度かかっています。診断書の記載内容に不明な点があったり、整合性がないなど、医師への照会などが必要な場合は決定まで更に長い時間がかかることがあります。
障害年金申請のための書類はどこでもらったらいいのでしょうか?
年金事務所(旧 社会保険事務所)か、市区町村役所の(年金)担当課です。
日本年金機構のホームページからダウンロードできるものもあります。
これまでに厚生年金に加入したことのある方、第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている妻や夫)期間のある方は、保険料納付要件の確認のため、まずは年金事務所に行ってご相談ください。
20歳前(先天性など)に初診日がある方、国民年金第1号被保険者(学生、自営業者など)期間のみの方の場合は市区町村役場が窓口です。
診断書などの書類は「年金申請用の書類をください」というだけでは簡単にもらえず、初診日がいつか、納付要件があるのかなど受給できる可能性を確認してからでないと渡してもらえない場合がほとんどです。まずは初診日を確認しましょう。
精神の障害用の診断書、血液その他の障害の診断書など日本年金機構のホームページからダウンロードできる書類もあります。
最初から当事務所にご依頼いただいた場合は、書類はすべてこちらでご準備させていただきます。
○○という病気の請求経験がありますか?
障害年金の請求は「病名」ではなく、「症状」(障害の程度、状態)によって支給されるものです。

病名が同じであっても、症状の出方やその程度は個々人によって違います。
一般的な傷病についての知識が必要であることは当然です。色々な勉強会に参加し、また障害年金支援ネットワークを通じて情報交換を行い、知識の研鑽に努めております。
具体的な症状については、ご本人さまやご家族からの聞き取りを丁寧に行い、「他にこんな不便はございませんか?」と推測してお尋ねし、ご本人さまの個別的症状を把握することを何よりも大切にしたいと考えております。
すべての傷病について経験があるわけではございませんが、安心して当事務所にご相談、ご依頼ください。
どうしても○○という病気の請求経験がある方にお願いしたいという場合は、障害年金支援ネットワークを通して、経験のある社労士をご紹介させていただくことも可能です。
共済年金の請求代行、不服申立は社会保険労務士が行う業務として認められていません。
社会保険労務士が行うことができる業務は法律で定められています。
厚生年金法、国民年金法に関わるものはできるのですが、共済年金法については、取り扱える法律に含まれていません。そのため、共済年金への請求、審査請求を行って報酬をもらうと法律違反になってしまいます。
そもそも共済組合というのは助け合いの組織であるため、専門家の支援を想定していないと考えられます。大変申し訳ありませんが、無料できる範囲のご相談、アドバイスのみをさせていただいております。
障害年金請求のことで不安やお困りはありませんか?
障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。

お気軽にお問合せください
- 初診日の証明書はどうやって依頼したらいいですか?
- 初診日の医療機関にカルテが残っていないと言われたのですが?
- 第三者証明はどんな内容を書いてもらったらいいでしょうか?
- 社会的治癒として請求したいのですが?
- 審査請求、再審査請求をやってもらいたい
どのような相談でも結構です。お問合せをお待ちしております。
面談予約・業務依頼は
一般的な電話相談は こちらへお願いします

日曜・祝日・年末年始を除く日の
10時~16時(12~13時は休み)
固定電話からは
0120-956-119
(フリーダイヤル)
携帯電話からは
0570-028-115
NPO法人障害年金支援ネットワークでは全国の社労士が交代で無料の電話相談を行っています。
(ぽぷりサポート事務所はNPO障害年金支援ネットワークの会員です。)
事務所概要

ぽぷりサポート事務所
代表者:溝上 久美子
〒543-0055
大阪市天王寺区悲田院町8-26 天王寺センターハイツ502号
主な業務地域
大阪市/東住吉区/住吉区/
平野区/阿倍野区/住之江区/西成区/天王寺区/生野区/
東成区/此花区/大正区/港区/中央区/浪速区/西区/北区/
城東区/福島区/旭区/都島区/
鶴見区/西淀川区/淀川区/
東淀川区/堺市/八尾市/
松原市